はじめに
30年以上働いた業界と全く異分野の森林での仕事を始めて、森林そのものだけでなく、そのビジネスにも興味が湧いている。そこで、『森林列島再生論』森と建築をつなぐイノベーションを読んでみた。
この本で、文月恵理さんが日本の森林に関する項目を紹介して、各分野の専門家が詳細に説明してくれている。文月さんも自分と同様に異業種から森林再生に興味を持った人である。ただ、文月さんの森林再生への熱意は20年近くも続いており、色々なことに挑戦してきた人。その熱意が伝わる本であった。
森林列島再生論 森と建築をつなぐイノベーション「森林連結経営」 新品価格 |  |
『森林列島再生論』森と建築をつなぐイノベーション
森林産業のビジネスモデル
「3本の矢を放て!』と主張している。
- 1本目の矢:住宅部材用大型パネルのサプライヤーチェーンの構築(森林資源と建築需要の需給情報見える化)
- 2本目の矢:木質バイオマス(バイオマス燃料への提唱し続けるしくみの構築)
- 3本目の矢:輸出(建築部材の輸出)
以下は一例であるが色々な施策が提案されている。
- 地方の製材所による森林資源と建築需要の情報を繋げるハブ化
- 森林ファンド投資型森林経営(森林所有者と経営者を分離して、価値ある森林資産へマネジメント)
- 物流フローの強化による森林直販化
- ICT(情報通信技術)活用による森林資源の見える化と情報活用
簡単にまとめれば、
木材の需給情報と在庫(森林資源量)の情報を一元化して、垂直統合化のビジネスモデルにする。その手段として、建築用としては大型パネルが有効であり、バイオマスの燃料として資源を最大限有効活用する。さらに、工場でサッシや梁などで付加価値をつけた建築部材により輸出の拡大を狙うという提案。
経営の視点で最も重要なことは、立木を適正価格とすること。そのために、有効の手段として、森林ファンドによる投資型森林経営である。
近年、サステナビリティーに対する意識が高まり、企業はSDGs(持続可能な開発目標)およびESG(環境・社会・ガバナンス)課題への対応が企業の価値やブランドイメージを向上させることができると注目されている。そして、二酸化炭素排出量とオフセットするために、森林の二酸化炭素吸収および貯蔵量をクレジット化したカーボンクレジットの販売など木材販売以外の副次的な収益源が見通せるようになってきている。
ただし、カーボンオフセット市場には課題。「排出削減・吸収の確実性と永続すること」、「二酸化炭素排出削減・吸収量を正確に算出すること」、「クレジット取引価格が高いこと」など課題は多い。そのため、政府の認証した二酸化炭素排出量削減を売買できる「森林由来のJークレジット制度」での森林由来クレジットは低調な状況。国による制度の見直しやモニタリング強化が必要である。
※「森林由来のJ-クレジット」とは、森林の適切な管理(間伐、植林、再造林など)によって吸収された二酸化炭素を数値化し、その吸収量をクレジットとして認証して、売買すること。
日本の森林の状況
日本の森林率はフィンランド、スウェーデンについて世界第3位(OECD加盟国)である。このことについては、「ラオスは山の国と言われるけれど、日本はもっと山の国だった」という記事に書いた。
現状、日本の森林資源は豊富である。この本では定量的に説明されており、わかりやすかった。
日本には森林備蓄量が約52億㎥ある。一方、日本の木材使用量は8000万㎥(うち3000万㎥が国産材)である。森林は日々成長しており、毎年億単位のペースで増加しており、木材使用量より十分多く、森林資源としては潤沢である。
コロナ終結とウクライナの戦争開始の頃から世界的なインフレで、物価が上昇し、色々な資源の入手が難しくなっている。木材も同じで、「ウッドショック」と言われる状況で、世界的な木材価格が上昇している。また、木材は体積が大きく、海上輸送の値上がりの影響も受けやすい。国産木材を有効に活用しやすくなっている環境が整ってきている。
さらに、日本の森林は戦前、戦中の過剰伐採とその後の大量植林により、伐採適齢期を迎える木々が多く存在している状況。
しかしながら、現在の立木の売買額は安すぎる状況。立木の価格(体積あたり)は大根より安いという。大根は畑で毎年収穫できるが、立木の収穫には50年以上もの時間を要する。大根の価格は、10万円/㎥で、スギの原木は約1.8万円/㎥、スノキの原木でも約2.7万円/㎥にすぎない。以上のような状況であり、立木を適正価格にする施策が必要である。
日本の林業の実情として、人手が足りていない。木を伐採して、再造林できるのは多く見積もっても日本の人工林1020万ヘクタールの半分の500万ヘクタール。50年サイクルとすると、毎年10万ヘクタールの伐採・再造林が現実的である。その場合の木材供給量は4000万㎥となり、今の日本の木材使用量の半分を賄うことができる。将来的には、日本の人口は減少していくので、大半の木材を供給できることになるという試算である。
いずれにしろ、日本には成熟した大量の人工林があり、それを活用し、次世代に引き継いでいくというのが大切である。
まとめ
『森林列島再生論』を読了した。必ずしも専門家の著者たちの意図を理解しているとは限らないが、「日本の森林の状況」の把握と「森林産業のビジネスモデル」について自分なりの理解を上記にまとめてみた。
情報を一元化し、垂直統合モデルというのは必要。また、いかにお金をこの森林産業に取り込むことも重要である。
いずれにしろ、日本の豊かな森林をしっかりと活用し、育成していく社会およびビジネスモデルを構築していかなければならない。
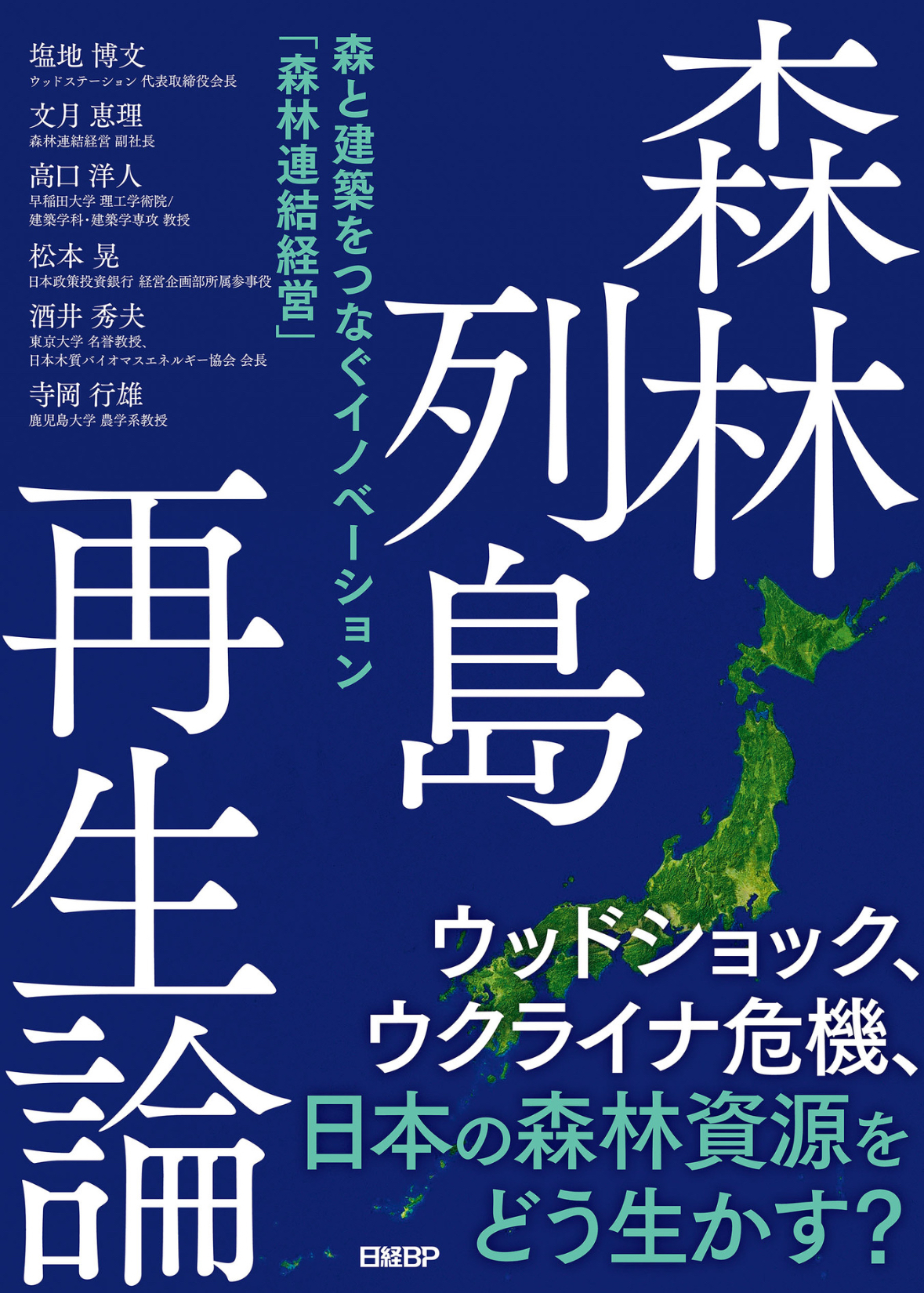



コメント