宮本常一氏とは
宮本常一氏は、明治40年生まれの民族学者。「歩く学者」とも称され、生涯にわたり日本各地の農山漁村を訪ね、人々の暮らしや文化、経済を研究した。「歩く・見る・聞く」ことを大切にしながら地域の人々と交流し、その生活の移り変わりを記録した。代表作のひとつは、「忘れられた日本人」である。
個人的には、「歩く・見る・聞く」という現場第一主義っぽいところが好きである。
新品価格 |  |
新品価格 |  |
「日本文化の形成」を読んで
ベトナム、中国、ラオス国境にまたがった地域に住む少数民族を巡って、日本人に顔つきだけでなく、自然崇拝(アニミズム)という考え方も日本人に似ていると感じた。そのため、日本人は一体どこからやってきたのか興味を持つようになっている。
『「日本人はどこから来た」を知りたくて、古代DNA展にいってみた』という記事を以前書いた。
宮本常一氏の「日本文化の形成」という本に、どのように日本列島に人々が移り住んでいるか書いてあり、興味深かった。
エビスたちの列島
「エビス」を漢字で書くと、「夷」と書くことが多いが、「蝦夷」とも書いた。「蝦夷」は、「えみし」「えぞ」とも読む。
「えみし」と言えば、蘇我蝦夷(そがのえみし)がいる。蘇我蝦夷は大和の飛鳥で大きな勢力を持っていたが、西暦645年の大化の改新で中大兄皇子と中臣鎌足に攻められて、自殺している。なぜ、大和で勢力を持っていた人が蝦夷(えみし)と名乗っていたのかというと、もともと日本列島に住んでいる原住民であったからと、宮本常一氏が説明している。彼らは、毛深く、たくましく、力強くて、多くの人々に畏敬され、尊敬されていたと推定している。
日本列島に古くから住んでいて、狩猟や漁労に従っている人を蝦夷(えみし)と呼ばれたのであろう。のちに、大和朝廷と接触した「蝦夷」と比較的接触の少なかった「蝦夷」に別れていった。そして、接触の少なかった東日本以北に住む「蝦夷」は緩やかに「えぞ」となり、未開を意味するようになったと、宮本常一氏は推定している。
歴史で習った大化の改新は、政治改革であったと教えられたが、じつは原住民(蝦夷:えみし)から渡来人への権力の移行だったのかもしれないというのが興味深かった。
大化の改新は、645年6月12日、飛鳥板蓋宮の乙巳の変(蘇我入鹿の暗殺による蘇我氏の滅亡)に始まる一連の国政改革。 狭義には大化年間(645年 – 650年)の改革のみを指すが、広義には大宝元年(701年)の大宝律令完成までに行われた一連の改革を含む。
ウィペディアより
ウキペディアの説明では、権力争いや改革にしか見えない。
また、日本列島に土着していた人々を「土蜘蛛」とも呼ばれた。「土蜘蛛」は大和朝廷に従わず、敵対した人々。だから、能で「土蜘蛛」というのがあり、「土蜘蛛」という鬼を退治する話があると知った。
ほんの1400年前の日本列島は土着の人々と渡来人がまだまだ融合していなかったのだ思った。
稲作を伝えた人びと
縄文時代は狩猟の生活で、縄文時代の終わり頃に稲作が日本に伝来した。お米は大きく分けるとジャポニカ米(短粒米)とインディカ米(長粒米)に分けられる。日本のお米は、ジャポニカ米であり、ルーツを辿るとメコン川に沿って雲南に通じている。まさに、6月に自分が旅をして、本に書いたルートでだった。
雲南省・ラオス 2025年旅日記&ガイドブック (ガイドブック 旅日記 トラベル 旅行 ) 新品価格 |  |
雲南省は地形的に高地もあり低地もある。標高1750m以下(年平均17℃以上)ではインディカ米の栽培地帯。標高2000m(年平均16℃以下)を超えるとジャポニカ米の栽培地帯となる。
日本に渡来したジャポニカ米の原産地は、ヒマラヤの東および東南の山麓であるとすると、そこから流れ出ている川は、揚子江、メコン川、チャオプラヤ川、イラワジ川などがある。そのうち日本に関わりのあるのは揚子江である。その支流の上流域で栽培され始めた稲が加工付近に伝播し分布するには、約4000年の歳月を要しているという。遺跡の発掘によると、日本に伝来した稲は、乾田であった。伝来したジャポニカ米は、乾田栽培に適しており、稲作の普及は、低湿地帯より傾斜地やデルタなの水を引けば水田になり、水を落とせば乾くような土地が多く利用されていたことも関連している。
標高2000m(年平均16℃以下)の地域に住む人々が栽培していた稲が日本に伝来しているというのが濃厚であると、本を読んで理解した。だから、ベトナム、中国、ラオス国境に跨った住む少数民族が日本人に似ているのだと思った。
また、6月に旅をした雲南省の麗江郊外の風景が、奈良(やまと)の田園風景と似ていた。ジャポニカ米の栽培に適していたから、古代は大和王朝が栄えたのかもしれないと思った。

司馬遼太郎氏の「街道をゆく20 中国・蜀と雲南のみち」より
司馬遼太郎氏の「街道をゆく20 中国・蜀と雲南のみち」にも少数民族が日本の稲作の祖と推測をしている。
以下は推測だが、稲作はいきなり長江が洗う大平野で成立したものではなかろう。はるかに江をさかのぼり、山谷の渓流の支流支流で発達したものがやがて江をくだり、楚や呉・越という大人口を擁する勢力になったかと思える。
となれば、こんにち、四川省、貴州省、雲南省などの山谷で稲をつくっている多種類の少数民族こそ、古代楚文化の末裔ということになる。長江流域の低地平野に降りてきて楚という古代稲作王国をつくったかれらは、やがて中原に発達した漢文明に同化され、紀元前の秦・漢帝国の成立で名実ともに中国の一部としての歴史に参加した。そのころには、はるかな上流の渓谷に残留した同文化の者を蛮狄視するようになる。たとえば、雲南あたりの少数民族をひっくるめて中国内地のひとたちが「西南夷」とよんできたということは、すでにふれた。このうちの稲作の蛮夷こそ、日本稲作の祖であったろうという推測は、大まかなところでは、たれもが異論のないところにちがいない。
(中略)
雲南省だけで、二十二種の少数民族がすんでいる。まさに民族文化の生ける博物館といっていいが、このうち、古代以来、山谷に集落をつくって稲作をしている民族たちを、私どもは自在に選んで日本稲作文化の祖にしていい。民俗がおどろくほど似ているのである。万葉の世のそのままの嬥歌(歌垣におなじ)が生きている民族が多く、また日本の平安期そのままの妻問婚が生きている民族もあり、その過程として当然、若者が夜、娘の家に忍んでゆく呼ばいもある。妻問・呼ばいなどは、日本の農山漁村で明治期まで生きていた。むろん、漢民俗社会や朝鮮社会ではありえないことである。
街道をゆく20 中国・蜀と雲南のみち(司馬遼太郎)より
ということで、今度はベトナム北部の最後のフロンティアと呼ばれるハザンに行って、少数民族をめぐる旅の計画を始めた。時間に余裕があれば、4月に旅をしたサパも訪問したいと考えている。
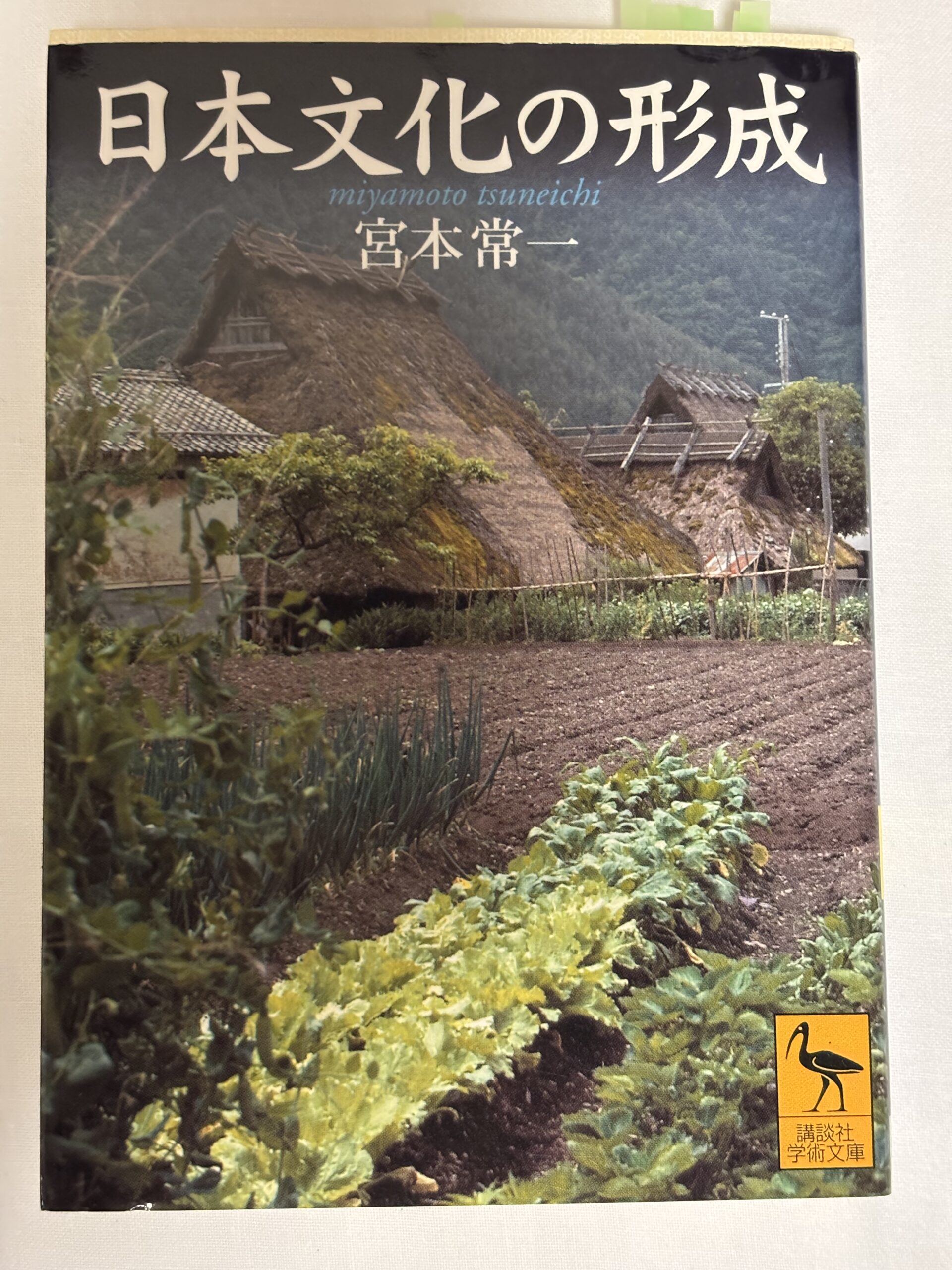
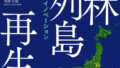

コメント