はじめに
白洲正子さんのことを知っていたが、華族出身で自分とは住む世界が違いすぎて、今まで白洲正子さんの書いた本を読もうとしていなかった。父が遺した本の中に白洲正子さんの本がいくつかあったので、「新版 私の古寺巡礼」を読んでみた。父は生前に、「僕の大和路」というテーマで写真を撮っていたので、撮影地をより深く理解するために白洲正子さんの本を読んでいたものと思う。
本を読んでみて、白洲正子さんは平易な文で書かれていて、分かりやすいことが意外だった。また、勝手に寺社仏閣や仏像などについて含蓄があるのかと思っていたが、そんなことはなく、自然体でお寺を訪問していることに共感をもった。だからかもしれないが、書かれているところに行ってみたいという衝動に駆られる良い本だった。
白洲正子著「新版 私の古寺巡礼」
古寺を訪ねる心
白洲正子さんは、「お寺を訪ねる心なんて持ち合わせていなかった」と言っている。「ぼんやり眺めて、なるべく楽しんで、いい気持ちになって帰ってくるだけ」という姿勢。向こうから近づいてくるものを、待って捕まえる。白洲正子さんは何に対しても、そういう態度で接しているとのこと。
自分もガイドブックを見て、何でも見てやろうという姿勢はなく、出かける時は事前の情報は過多にならないようにしている。情報が多すぎると、事前に知ってしまった情報を辿る旅になってしまう。旅では予想をしていなかったことに出会う機会を多くしたいと思っている。
「自分の旅に対する姿勢が良いのか?もっと事前に旅先の情報を調べて、網羅的に調査して、ブログを書いた方が良いのか?」と少しもやもやしたものがあったが、この本を読んで、自然体で良いんだ。と認識させられた。
「信仰なんかなくても構わない。ひたすら歩けば良い。」という言葉は、自分の「歩く旅・走る旅」と近くて少し嬉しくなった。白洲正子さんは、「なるべく古い巡礼道を歩くように心がけて、車でいきなり乗りつけると、興味が半減する」とも言っている。熊野古道を歩いて行って、遠くに大斎原の大鳥居が見えて、熊野本宮に辿り着くのと、車で乗りつけるのでは、受ける感覚が全然違うというのも自分で実感している。

効率的な旅ではないけれど、今後も「自然体で、歩く旅・走る旅」を続けていきたいと思った。
南河内の寺
本を読んで、「西国巡礼」をしてみたくなったし、「十一面観音巡礼」というのも興味をもった。
白洲正子さんの文章は、平易な文で書かれているが、情景が眼に浮かぶ。「南河内の寺」では、近鉄南大阪線に乗って、河内長野に向かっている。大阪に住んでいる人でもあまり行ったことのないエリアである。秘境というエリアではないが、一つの国どんづまりという表現はわかるようなような気がした。紀州と大和を結ぶ裏街道で、秘密にみちた「隠国(こもくり)」である。そのようなエリアであるから南朝の隠れ家ともなった。
「金剛寺」にも行ってみたいと思った。女人禁制の高野山と違って、「女人高野山」と呼ばれている。隠国で裏街道をいく「金剛寺」に魅力を感じた。
自分が知らなかっただけかもしれないが、国宝も5つある。
- 木造大日如来坐像
- 木造不動明王坐像
- 木造降三世明王坐像
- 延喜式 巻十四
- 日月四季山水図
「日月四季山水図」は特に逸品とのこと。四季が美しい色彩で描かれた6曲1双の屏である。自然体に作品に向き合って、感じたことをしっかりと分かりやすく書いている。
片方は、春から秋へかけての風景で、重なり合った山の向うに、日輪が輝き、もう一つの方は、雪の山に月がかかっている、大胆無比な構図である。一説には、那智を写したともいうが、一種の宗教画であることは確かだろう。日本の風景画は、自然を拝むことから発達したが、拝む心を持たないものに、このように崇高な景色は描けなかったに違いない。
春景色の方は、この辺の山の姿にそっくりで、雪の山は、葛城であろうか。眺めていると、これはやはり那智ではなく、金剛寺に住んだ画僧が、自然と長い間つき合って、すっかり自分のものにした後、心の中の風景を描いたように思われて来る。桃山時代という説もあるが、そこにただよう静かな風韻、浪の描写の軽さなど、桃山の豪華さと押しつけがましさはなく、むしろ宗達の手本になったような気がしないでもない。
自分がこの絵に向かい合った時にどのように感じるのか訪問が楽しみである。
 | 新品価格 |
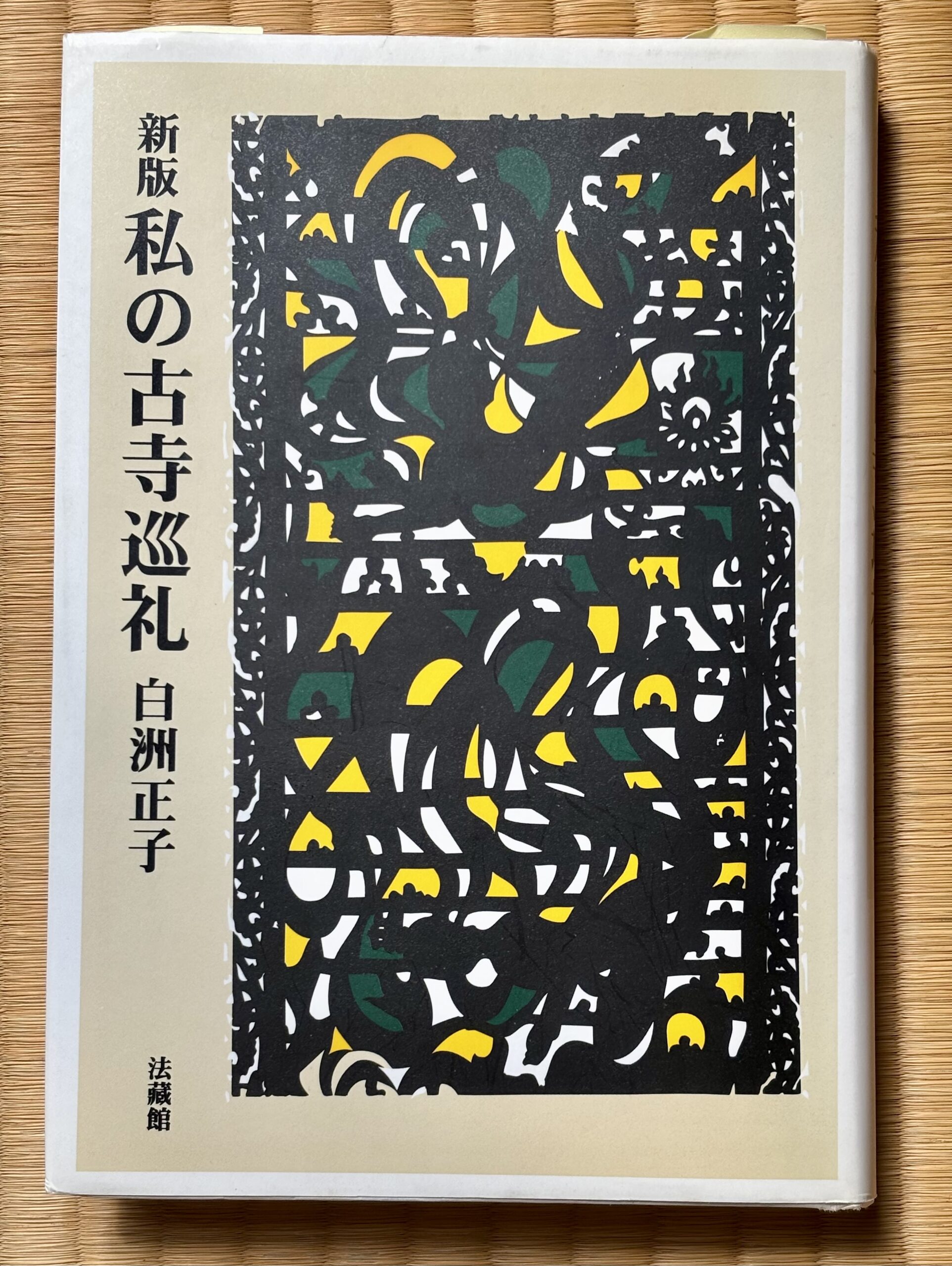

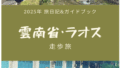

コメント