稲垣栄洋さんの「雑草と日本人」
雑草が褒め言葉なのは日本人だけ
この本は、誰もがあまり取り上げない雑草を主題として取り上げている。そして、雑草が日本人の考え方や国民性に与えた影響について考察している本である。
「雑草」という言葉が褒め言葉なのは、日本人だけであるとこの本では言っている。日本人は雑草の好きな国民である。例えば、『雑草魂』という言葉がある。踏まれても挫けないと言う意味。日本人にとっては良い意味。温室育ちのエリートより『雑草魂』の方が好まれる。
元プロ野球選手の上原浩治選手が『雑草魂』を座右の銘としていた。プロ野球で活躍するほとんどの選手が甲子園や脚光を浴びる場所で活躍していたのに対して、上原選手は高校時代は控え選手、大学入試でも失敗し18歳で浪人を経験するというまさに「雑草」のようなところから這い上がり、ワールドシリーズでも優勝と『雑草魂』をまさに表している。スピードガンでは遅い速球とフォークだけで、バタバタ三振を取る投球スタイルも痛快である。
「雑草」は、日本でも外国でも厄介なものであることには変わりはない。それどころか、日本の雑草の方が、高温多湿で多雨と言う気候であり、放っておいてもすぐに伸びてしまう厄介なもの。この本では、なぜ日本人は褒め言葉に使うよう、雑草に愛着を持っているのかを考えている。
 | 文庫 雑草と日本人: 植物・農・自然から見た日本文化 (草思社文庫 い 5-4) 新品価格 |
先進国でアニミズムが残っているのは日本だけ
日本は先進国でありながら、アニミズム的な思考が根強く残っているのである。
アニミズムとは、
仏教や神道にはさまざまな神さまがいて、それら複数の神を信ずるのが多神教である。日本は、多神教であると言われる。しかし、多神教どころではない。日本には神社や仏閣だけでなく、台所にもトイレにも神さまがいる。川にも田んぼにも神さまがいる。このような万物に霊が宿るというのは、アニミズムと呼ばれる自然信仰である。
「日本人にはアニミズム思考が残っている」と、ラオスのジャングルの中で一緒に旅をした中国人のタイガー君にジャングルの中で力説したことがある。「雲南省•ラオスの旅⑩ ルアンパバーンからモン族とカム族の村を巡る」の記事に書いている。
外国人から見れば、日本は発展した国。東南アジアの少数民族のようなアニミズム思考があるとあまり知られていないる。
なぜ先進国である日本にアニミズム思考が残っているのか?
豊かな自然と自然災害の多さだとこの本では言っている。
例えば、森に入った時、周りの木々や風に揺れる草花や、大きな石に気配を感じることがある。昔の人は、この感覚を神と感じたのかもしれない。日本だけでなく、古代の宗教は自然への恐れや敬いからなっていた。そのため古代宗教は多神教であることが多い。日本の八百万の神に見るように、多神教の神々は私たち人間と同じように自然の恵みを享受し、自然の中で生きている。
一方、自然の恵みが豊かでない砂漠ではそのような気配を感じられないのだろう。天の神に救いを求めて一神教の考え方になる。自然は恵みをつかさどるものでなく、克服するものであると言う考え。トレイルランナーの鏑木剛さんが、日本の山には祠があったりして山には神がいるけど、西洋の山にはデビルがいると言っていた。西洋人にとっては、自然は克服するものであり、敵対する存在なのだろう。
一般的に、近代化されて自然が少なくなれば、アニミズム思考は失われていく。日本人がそうならなくなった理由は、自然災害(台風、地震、火山など)の多さだと言う。自然の力の大きさと人間の小ささを思い知らされ続けたからである。そのため、先進国にも関わらず、日本にはアニミズム的な思考が根強く残っていると考えている。
日本人にとって「雑草」はなぜ褒め言葉なのか?
日本人は、神社で商売繁盛や合格を祈願したり、豊穣を祈念したりする。その一方、厄除けに代表されるように、平穏無事を祈ることも多い。恵みを求めるというより、自然の脅威がないように願うことも多い。日本人にとって、自然の恵みと自然の脅威は、表裏一体である。
人と自然の戦いは、戦いの中で友情が芽生える良きライバルのような関係だったのかもしれない。そして、日本人にとって、雑草もまた強力なライバルだったはず。日本の雑草は、西洋の雑草と比べて手強い。田んぼや畑の雑草を抜いても抜いても生えていくる。抜かないと収穫量が減っていしまう。日本人は、雑草に悩まされながらも、雑草を手強い相手であり、一目を置くような存在になっていったのだろう。そして、雑草が褒め言葉に使われるようになったのだろうと考えられる。
「雑草」と日本人の国民性について
日本は自然が豊かであり、田畑を雑草を抜くなどしっかり管理すればするだけ、収穫が得られる。しかし、働くことをやめれば収穫は皆無である。怠けることを許さない。しっかり管理するためには、手強い雑草を抜く必要がある。この雑草との戦いが、一つ一つの仕事を手を抜かずにていねいに行う日本人の勤勉性を育んできたのではないだろうか。
さらに、日本人の協調性は、度重なる自然災害によって育まれたのだと考えられる。東日本大震災のような厳しい状況に置かれても、規律正しく行動する。それが、長い目で見れば、最適な行動基準であるということを日本人は身に染みて感じているのだろう。
阪神優勝と「雑草魂」について思うこと
上原浩治選手が『雑草魂』を座右の銘としていたを書いた。
今年の阪神が強いのはこの『雑草魂』を持った選手が多いからではないだろうかと思う。近年の阪神のドラフトは成功している。しかし、選手を選ぶ球団の基準が技術だけでなく、選手の人間性(真面目、謙虚、素直、努力する人材)を見て、ドラフトしているのではないだろうか。
阪神の野手の1番から5番打者の5人。東海大相模高校出身の森下選手以外は、野球エリートには見えない。近本選手と佐藤選手は、普通の公立高校で甲子園とは無縁であった。投手を見ても、エースの才木選手は同じく公立高校で甲子園とは無縁であった。『雑草魂』を持った選手に思える。
もう一人のエースの村上選手は野球エリートだが、自分が降板した後でどんな厳しい状況であっても、ニコニコ応援している姿を見ると、人間性の良さが窺い知ることができる。
阪神のドラフトで、特徴的なのが、石井選手と早川選手。石井選手は、プロ野球初の高専出身。プロに挑戦したくて、独立リーグ経由でドラフト8位で入団。球団連続無失点を更新中であるが、真面目で努力する選手。早川選手は公務員から育成選手で阪神に入団し、9月に初勝利をあげた。野球に賭ける情熱がすごい。このような選手がいるから阪神強いのだろうと思った。
また、そういう人材を活かせるのが藤川監督。ドラフト1位で入団したけど、活躍する6年くらい掛かっている。その時の苦労が、今の若手の育成に役立っているのだろう。順調にいくに越したことはないけれど、途中回り道しても、将来それを活かすことの大切さを感じた。
会社でも、和を乱すエースより、多少成果が少いがコツコツ仕事をする和を尊ぶ人の方が好みだった。最終的にチームとしてのアウトプットは増えるし、チームも成長する。若手であれば、成果が少なくも素直で真面目が化けると思っている。
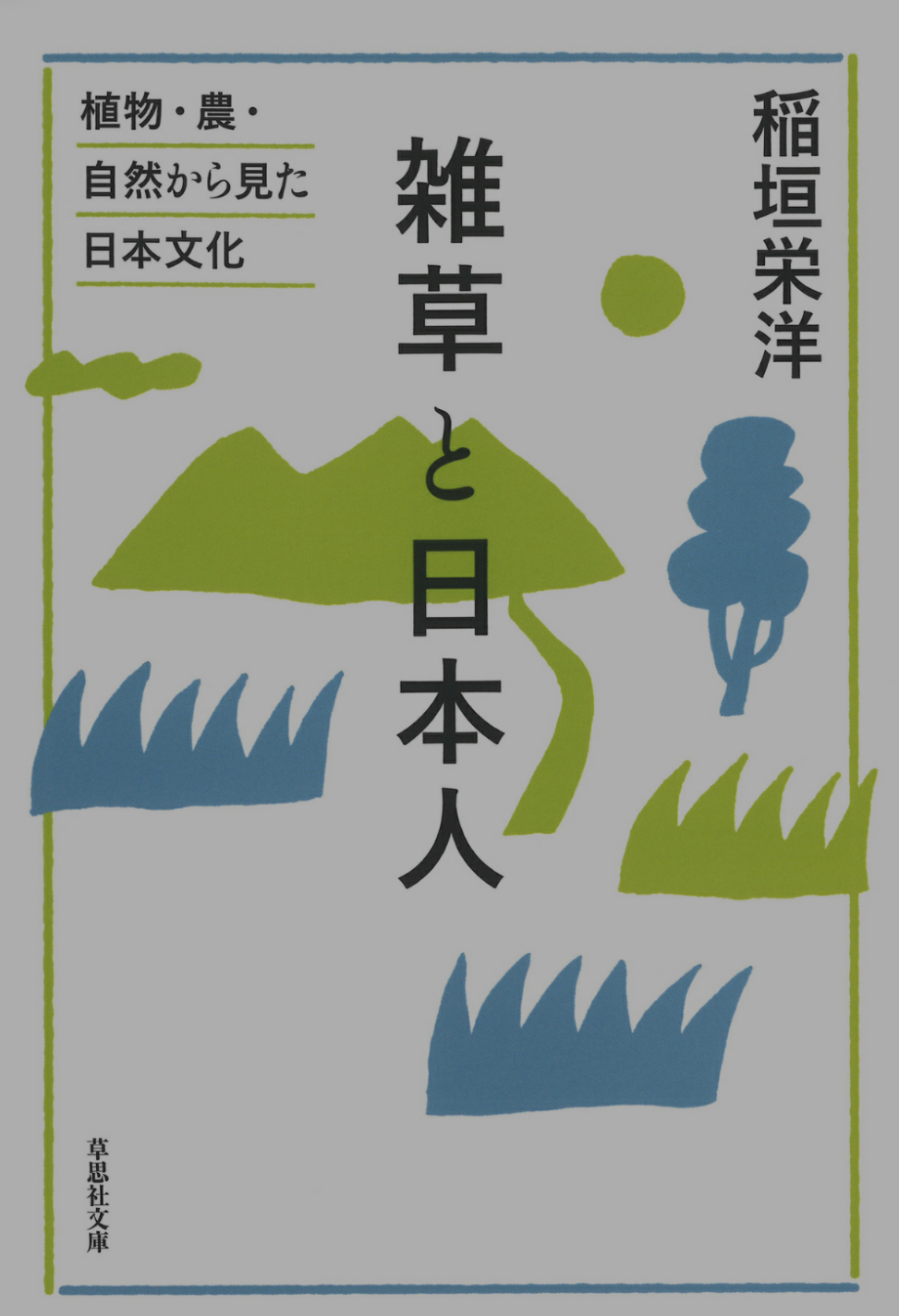


コメント