はじめに
本多静六氏の名前は知っていましたが、昔の投資家と思っていました。というのも、Amazonで書籍を調べると、近代経済人文庫で「私の財産告白」やら「私の人生計画」などが並んできます。
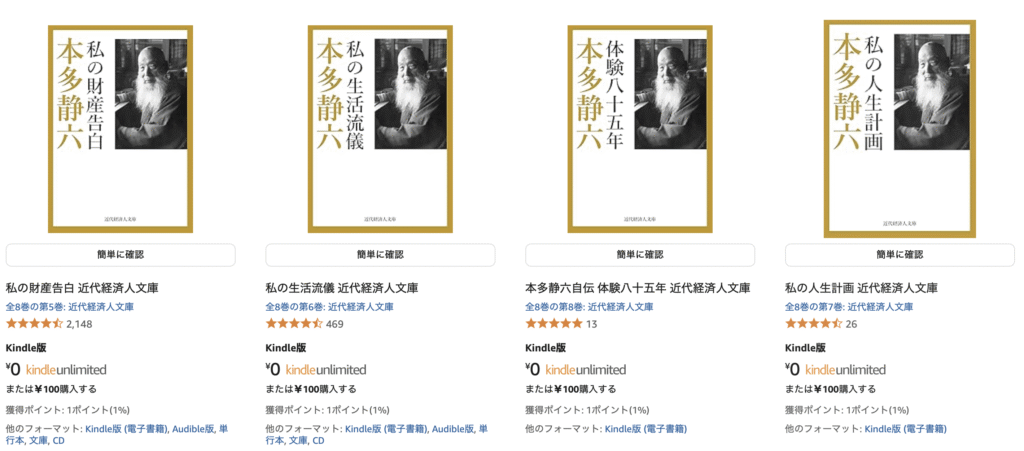
「森林ビジネス」を読んで、日本初の林学者だと知りました。明治神宮の杜を作った人であり、前回の記事『古川大輔さんの「森林ビジネス」を読み、明治神宮の杜で考えた事』で明治神宮に行ったことを書きました。林学者の本なら読んでみようという気持ちになりました。
「本多静六 合本版」、「職業は道楽の如く 貯金は四分の一 本多静六33の成功哲学」を読む
いずれもAmazon Kindle Unlimitedで読むことができました。
「本多静六 合本版」の全文は長いです。すぐ読むことができる「職業は道楽の如く 貯金は四分の一 本多静六33の成功哲学」を読んで、「本多静六 合本版」は流し読みをしました。
「職業は道楽の如く 貯金は四分の一 本多静六33の成功哲学」は、本多静六氏の本のエッセンスを現代風に編集したものです。短時間に要点を理解するのに良い本です。分かりやすく書かれており、共感できることも多かったです。
 | 新品価格 |
 | 新品価格 |
貯蓄と財産形成と使い方
なぜ林学者である本多静六氏が巨万の富を得ることができたのか?
非常にシンプルな取り組み方です。収入の4分の1を安全に投資(知識のある山林投資と株式投資)して、自制心を持つ(規則正しい生活、貧乏を恐れず浪費を恐れる)ということ。そして、遺産は社会に貢献するために生きている間に使うということ。自分を律して、それをやり切るというのが凡人にはなかなかできない。お金が貯まると人が変わることもあり、自制心というのが一番難しいのかもと思いました。
人生設計
人生を4つに区切って、目標と立てて、人生設計をする。
1.準備期(〜25歳):勉学の期間
2.実行期(25~50歳):専門性を高めるために仕事に打ち込み、経済的な自立を目指す
3.指導期(50〜75歳):今までの専門性を活かしつつ、社会に貢献(第2の人生)
4.安楽期(75歳〜):余生を楽しみつつ、これまでの経験を次世代に伝える
50歳で引退(人生の方向性を転換という広い意味)するためには、それまでに専門性を深めて、経済的な自立を目指す。50歳で「第2の人生」を始められように準備をする。
本多静六氏は、50歳で大学を退官して、社会に貢献するための活動を行いました。その成果の一つが明治神宮の杜の育成でした。そして、築いた財産を学校や公共施設の建設に寄付をしました。
なかなかこのような人生は送ることは難しいですが、4つに区切るというのは、自分がぼんやりと思っていた感覚と近くて、共感しました。
働き方と職業観
仕事に対しては、「仕事を単なる生活の糧として捉えるのでなく、自分の情熱を注げる道楽のように楽しむこと」という姿勢です。どんな職業であっても、その中に面白さや意義を見出すことができると言っています。
確かに、林学っていうのは地味です。このブログに森林のことを書いてもアクセス数は少ないです。ただ、本多静六氏は、森林も持つ奥深さに魅了され、道楽のように研究しました。
道楽のように仕事をするためには、仕事の本質を理解することが大切です。ここでイソップ寓話のレンガ職人の話を引用します。
旅人が、田舎の道を歩いていると男が、辛そうな顔をしてレンガ積みをしていました。旅人は男に、「何をしているのですか?」と尋ねました。
男は「見ての通りレンガ積みさ!俺は朝から晩まで、暑い日も寒い日も一日中レンガ積みをしているのさ」「腰は痛くなるし、手もボロボロさ、もっと楽な仕事をしている奴はたくさんいるのに、俺は本当についてないのさ!」
旅人は、男に慰めの言葉をかけてまた歩きだしました。しばらく歩くと別の男が、またレンガを積みをしていました。しかし、先ほどの男のように辛そうには見えませんでした。旅人はこの男にも「何をしているのですか?」と尋ねました。男は「レンガを積んで壁を作っているのさ」と答えました。旅人が「大変ですね」と声をかけると、男は「そんなことはないさ、ここでは仕事を見つけるのは大変で、仕事があるだけもありがたいことなのさ」「おかげで、俺は家族を養うことができているんだ」旅人は、男に励ましの言葉をかけてまた歩きだしました。
しばらく歩くとまた別の男が、レンガを楽しそうに積んでいました。旅人はこの男にも「何をしているのですか?」と尋ねました。男は「俺たちは歴史に残る大聖堂を作っているのさ!」旅人が「大変ですね」と声をかけると男は「とんでもない!俺たちが作った大聖堂で、多くの人が祝福され悲しみがはらわれるんだ」「俺たちは素晴らしい仕事をしているんだよ!」旅人は、男に感謝の言葉を残して、明るい気持ちで歩き出しました。
本多氏は3人目の男のような考え方をしていました。本多氏にとって、森林の研究は単なる学問ではありませんでした。森林は国土保全に欠かせないものであり、人々の生活を支える重要な資源です。また、美しい景観を作り出し、人々の心を癒す存在でもあります。こうした森林の価値を深く理解することで、研究への情熱を持続することができたのです。
さらに、「職業を道楽にするためには、創意工夫を楽しむことです。決まられたことをこなすだけでなく。より良い方法や効率的なやり方を常に考える。この探究心が仕事を面白くしてくれるのです。」とも言っています
仕事に対しては、出世することを目標にするより専門性を磨くこと。そうすると必要とされる人材になっていくことができると説明しています。
さらに、仕事に対しては、汗水を流すことに誇りを持つこと。実際に山に入り、木を植え、土を掘り、汗まみれになって作業することが大切とも言っています。私も、「現地・現物・現実」が大切だと思っています。
学びと習慣の大切さ
日常生活でも大切にしていることがあるとも言っています。「1日1ページの読書習慣をつけて、本を読んだら書いて考えよ」です。
今までの自分は、本を読んでも読みっぱなし。ブログを始めたのだから、読んだ本を積極的に書いていこうを改めて思いました。他の人に説明することで、自分の理解も深まり、新しい視点を持つことができます。そして、疑問に思ったことをされに深掘りするという姿勢でいきたいです。



コメント